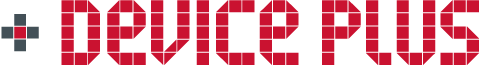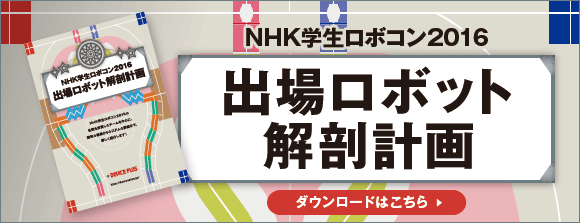全国の高専ロボコンに関わる学生が一同に集まり、交流を深める「第22回全国ロボコン交流会」が、2024年12月14~15日、兵庫県立総合体育館(西宮市)で開催された。参加者は全国38校から集まった約300人余り。出展されたユニークなロボットに見入ったり、気になるパーツについて質問したりと各校のブース前には人だかりが絶えない。現地入りした取材班より、レポートをお届けする。
12:30 開会式
開会式は例年通りのあいさつから始まり、続いて協賛企業が紹介された。前年からの変化については「参加校の多様化があげられます」と幹事団代表の若松さん(明石高専)は語る。参加校はもとよりブース展示を行う学校にも変化が見られるという。4年前からずっと幹事団の一人として関わってきた若松さんならではの感想である。

左・若松さん、右・土井さん
今年も参加希望者が多かったため、会場のキャパシティを考慮して参加人数が制限された。「せっかく来たいと思ってくれたのに、全員を招待できなかったのが何とも心苦しかった」と若松さん、土井さん(富山高専射水)は打ち明ける。選ばれて集まった参加者たち、だからこそ、みんな何かを得て帰ろうと目を輝かせている。外では寒風が吹きすさんでいたけれど、そんな若い人たちの熱気が寄せ集められた会場内は、一転して温かな空気で充たされていた。
13:00 ブース展示
屋内2か所の会場で、高専7校8チームと豊橋技術科学大学が自慢のロボットや技術を紹介するブースを出展し、参加者と交流した。会場内にはほかにも、OOEDO SAMURAI が、2024年8月に中国・深センで開催されたRoboMasterの世界大会に出場したロボットを展示していた。高専ロボコン2024「ロボたちの帰還」に出場したロボットも多数登場しており、その中からいくつかをピックアップしてご紹介する。

球形のロボットを開いて中の仕組みを見せて説明していたのが、長野高専のチーム「まるくあり隊」。同校の小笠原さんは「できるだけ丸い形での競技参加をめざしました」とデザイン性重視のコンセプトを説明する。
その狙い通り、このロボットは地区大会でデザイン賞・特別賞を受賞している。完成度の高い球体デザインからは、ロボットらしからぬ優しさが伝わってくる。しかし、このロボットはデザインだけではなく、その機体にオブジェクトを収める驚きの回収機構を有している。ただし丸いボディに駆動システムを納めなければならないため、フレームを曲げて組み込むなど製作の難易度は高かったという。
見学者は「こんな形のロボットをどうやって動かしているのか、その中身を知りたい」と小笠原さんを質問攻めにしていた。

向かいの長岡高専のブースでは「曲がる台車」が展示されていた。目を引いたのは、その段差を乗り越えるメカニズム、これは2023年のロボコン「もぎもぎ!フルーツGOラウンド」用に開発されたものだ。
最終的に本番機には採用されなかったけれど「段差越えに挑戦したユニークな機構を、ぜひ見てもらいたくて持ってきました」と五十嵐さんは語る。段差に乗り上げた段階で止まりがちになるケースが多いなか、いかに動き続けるかがポイントだ。そのための仕掛けが注目を集めていた。

地区大会で圧倒的なパフォーマンスを披露し、全国大会でも活躍した奈良高専の「射駒」も出展されていた。ブースではロボットを飛ばす射出機構について、パーツを手にとって見せながら説明が行われていた。「地区大会を終えて全国大会出場が決まった段階で、軽量化に取り組みシリンダーの太さを変えたり、ストロークを短くするなど、とにかくいかに軽くするかが課題でした」と藤田さんは苦労したポイントを振り返る。
同校のブースでは展示物を見て質問を繰り返しながら、きめ細かくメモを取っていた高専生の姿が印象的だった。自分たちだけでは思いもつかなかったアイデアと出会える、刺激を受けて発想が広がる、それが交流会に参加する何よりのメリットだ。

一方で、こちらも多くの見学者が次々と訪れては、飛び交う質問に対応していたのが豊橋技術科学大学ロボコン同好会「とよはし☆ロボコンズ」のブース。NHK学生ロボコンで3年連続優勝と高い技術力を誇り、世界を知るチームである。
そのメンバーたちが、完成品のロボットや各種のパーツを見せるだけでなく、タブレット端末も使って高専生たちの問いかけにていねいに答えている。「わざわざ交流会に来るほどですから、みんな向上心にあふれています。一つの問いに答えると、さらにいくつもの関連質問が飛んでくる。説明の際には学生ロボコンで使っている技術の、高専ロボコンへの応用の仕方を伝えるよう意識しています」と自らも鹿児島高専ロボコンOBの石原さんは参加した意図を明かす。実用的なアドバイスを得られるブースには、人だかりが絶えなかった。
スタートから早速、熱気があふれた交流会の会場。後編では、引き続き展示の様子と学生同士の交流についてお届けしていきたい。